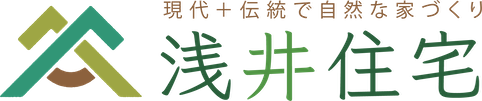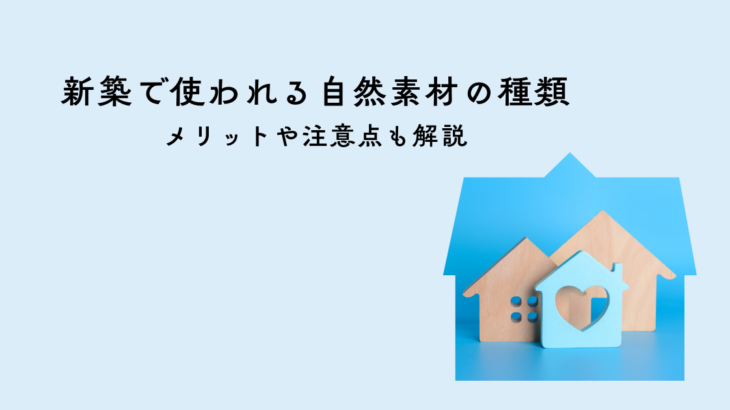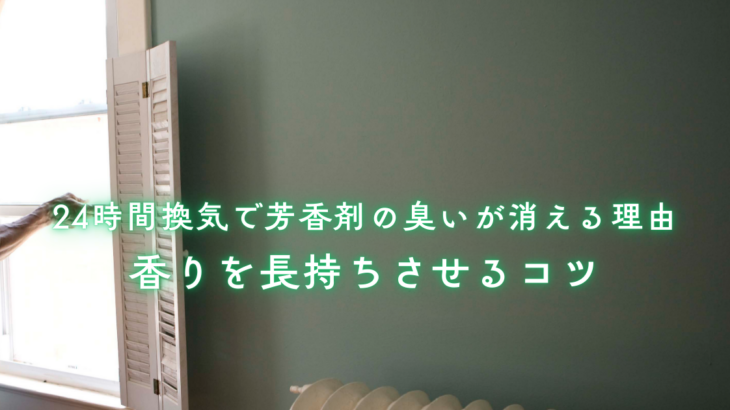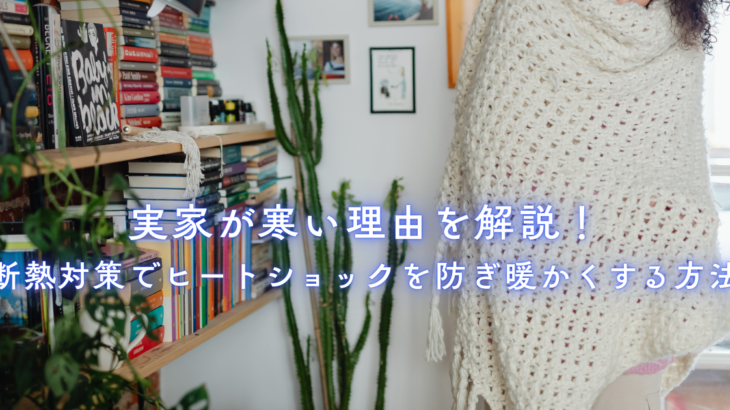快適な住まいづくりには、様々な要素が関わってきます。
その中でも、家全体の気密性能は、住み心地や光熱費に大きく影響する重要なポイントです。
新築住宅を検討する際、気密測定について、どの程度理解しているでしょうか?
この測定はいつ行うのが最適なのでしょうか。
また、測定結果が悪かった場合はどうすれば良いのでしょうか。
今回は、これらの疑問にお答えします。
気密測定の最適なタイミング
工事中に行うメリット
工事中に気密測定を行う最大のメリットは、問題発生時の修正が容易であることです。
測定結果が悪かった場合、すぐに原因を特定し、断熱材の追加や隙間を埋めるなどの修正工事が可能です。
完成後に問題が発覚した場合と比べて、大幅なコスト削減と工期の短縮に繋がります。
また、工事中の測定は、職人の施工精度を高める効果も期待できます。
数値化された結果が、彼らのモチベーション向上や責任感の強化に繋がるのです。
工事中に行うデメリット
工事中は、まだ設備機器の設置が完了していない場合があります。
そのため、仮設のドアや目張りなどを使って測定を行う必要があり、正確な測定値が得られない可能性も否定できません。
また、工事の進捗状況によっては、測定のスケジュール調整が難しくなる場合もあります。
測定のための準備や、測定後に行う修正工事によって、工事全体のスケジュールが若干遅れる可能性も考慮すべきです。
完成後に行うメリット
完成後の測定は、全ての設備機器が設置された状態での測定となるため、最も正確な気密性能が分かります。
また、完成後に測定を行うことで、施工全体の完成度を客観的に評価することができ、より安心感を得られるでしょう。
万が一、基準値を下回っていても、その後の対応について、建設会社とじっくり話し合う時間的余裕があります。
完成後に行うデメリット
完成後に気密性能に問題が見つかった場合、修正工事は困難で、高額な費用がかかる可能性があります。
既に内装が完了している場合、修正工事のために内装を剥がす必要が生じ、多大な時間と費用を要するでしょう。
場合によっては、住み始めてから問題が発覚するという事態も避けられません。
修正工事の難易度や費用は、問題の規模や場所によって大きく異なります。
気密測定結果が悪かった場合の対処法
測定結果の基準値と解釈
気密性能はC値(シー値)で表され、数値が小さいほど気密性が高いことを示します。
測定結果の解釈は、単なる数値だけでなく、建物の構造や気密化の状況なども考慮する必要があります。
専門家のアドバイスを受けることが重要です。
問題箇所の特定方法
測定結果が悪かった場合、まず問題箇所の特定が必要です。
サーモグラフィーカメラや気密測定器を用いた検査によって、空気漏れが発生している場所を特定します。
経験豊富な専門家であれば、測定結果から問題箇所の推測も可能ですが、目視確認を行うことで、より正確な特定が可能です。
原因を特定する作業は、今後の修正工事に大きく影響します。
適切な修正方法
問題箇所の特定後、適切な修正方法を選択します。
空気漏れ箇所が小さい場合は、シーリング材やパテなどで隙間を埋めることが可能です。
一方、大きな隙間や構造上の問題がある場合は、断熱材の追加や、部分的な改修工事が必要になる場合もあります。
修正方法は、問題箇所の状況や建物の構造によって異なり、専門家の判断が不可欠です。
安易な対応は、かえって問題を悪化させる可能性もあります。
再測定と確認
修正工事が完了したら、再度気密測定を行い、改善効果を確認します。
修正後のC値が基準値を満たしているかを確認し、必要に応じて追加の修正工事を行います。
再測定によって、修正工事が適切に行われたかどうかを客観的に評価できます。
安心できる住まいづくりのためには、この再測定が非常に重要です。
まとめ
新築住宅の気密測定は、快適な住まいを実現するために非常に重要です。
最適なタイミングは工事中ですが、完成後に行うメリット・デメリットも理解した上で、自身の状況に合わせて判断することが大切です。
測定結果が悪かった場合でも、適切な対処法を講じることで、問題を解決できます。
専門家のアドバイスを積極的に活用し、安心できる住まいづくりを進めていきましょう。
そして、気密性能だけでなく、換気性能についても十分に考慮することが重要です。